こんにちは。動物の救急病院で日夜戦っている獣医のSohey(ソーヘイ)です。
夜間救急の現場では、次の言葉をよく耳にします。
「目を離している間にチョコレート食べちゃったみたいなんです…」
特にバレンタインデーやクリスマスシーズンでは、あるある。
テーブルの上に置いていたチョコレートや、しまっていたはずのお菓子を食べてしまうケースが後を絶ちません。
ところで、チョコレートやキシリトール入りのお菓子が、
なぜ犬にとって危険なのか、ご存知ですか?
そこで、3回シリーズで犬の中毒に関する重要な情報をお伝えしていきたいと思います。
第1回となる今回は、救急現場で最も多く遭遇する「チョコレート中毒」と、
意外と知られていない「キシリトール中毒」の危険性について、詳しく解説していきます。
▼犬の中毒に関する連載記事
- 第1回:チョコレート中毒とキシリトール中毒(本記事)
- 第2回:タマネギ、ニンニク、ブドウの影響(予定)
- 第3回:家庭内の意外な危険物質(予定)
この記事を読んで、大切な家族である愛犬を守るための知識を身につけていただければと思います。
チョコレート中毒
チョコレートの危険性について
犬のチョコレート中毒を引き起こす原因は、
主にカカオに含まれる「テオブロミン」という物質です。
このテオブロミン、人間の体内では比較的早く分解されるため、
私たちは安全に食べることができます。
しかし、犬は肝臓の酵素活性が低いため人間と比べて代謝が遅く、
長時間体内に留まるため毒性が蓄積されやすくなるのです。
その結果、以下のような症状を引き起こしてしまいます。
チョコレート中毒の症状
・嘔吐
・下痢
・多飲多尿(多く水を飲んで多くおしっこをする)
・興奮
・心拍数の上昇や不整脈
・けいれん(重症例)
どれだけ食べたら危険なの?
チョコレート中毒の危険度は、カカオ(テオブロミン)の含有量に比例します。
そして、チョコレートの種類によってカカオ(テオブロミン)の含有量が変わってきます。
ホワイトチョコレートはカカオ成分はほとんどなく安全ですが、
ミルクチョコレートやダークチョコレートにはテオブロミンが含まれています。

同じ量を食べた場合、
ダークチョコレートはミルクチョコレートの2〜5倍程度の危険性があります。
| チョコレートの種類 | テオブロミン含有量(mg/g) | テオブロミン100mg 相当量(g) | 中毒量目安 (5kg犬: 100mg〜) | 痙攣発生量 (5kg犬: 300mg〜) | 致死量目安 (5kg犬: 500mg〜) |
|---|---|---|---|---|---|
| ホワイトチョコレート | ごく微量 | - | リスクほぼゼロ | リスクほぼゼロ | リスクほぼゼロ |
| ミルクチョコレート | 1~3 mg/g | 33.3~100 g | 33.3~100 g | 100~300 g | 166.7~500 g |
| ダークチョコレート | 5~15 mg/g | 6.7~20 g | 6.7~20 g | 20~60 g | 33.3~100 g |
| カカオパウダー | 15~25 mg/g | 4~6.7 g | 4~6.7 g | 12~20 g | 20~33.3 g |
注意;上記表は目安になります。
チョコレート製品のテオブロミン含有量は種類/商品によって異なります。
上記表の量より少ない量の摂取でも、感受性や体調などによっては重篤な影響がでることもあります。
犬は体重が軽いため相対的に人間より大きな影響を受けやすく、
チョコレートの香りに惹かれて大量摂取してしまうと危険度も跳ね上がります!
チョコレートの大量誤食でチョコレート中毒の症状が出なくとも、
チョコレートの脂肪や糖分などの影響で下痢や嘔吐などの消化器症状が起こる可能性を忘れてはなりません⚠️
キシリトール中毒
なぜキシリトールが危険なのか
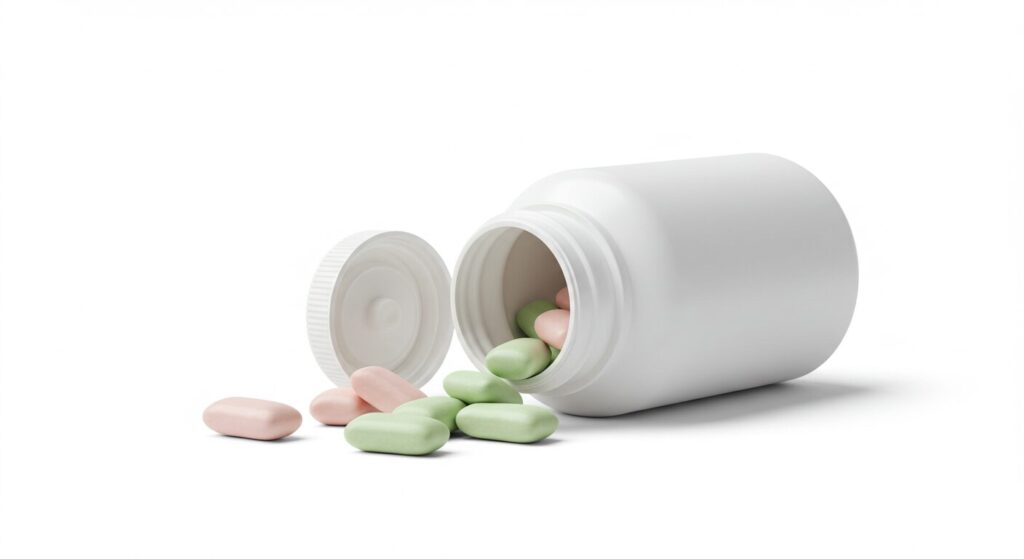
キシリトールは食品やお菓子、歯科医療にて使用する人工甘味料の一つです。
人間の体では安全に代謝できますが、犬の体ではとても危険な反応が起こります。
では、どう危険なのでしょうか?
それは、犬の体が「キシリトール=糖分」と勘違いしてしまうからです。
人間の体では、キシリトールは単に「甘い」と感じるだけで血糖値は変化しません。
しかし犬の体は、この「勘違い」によって血糖値を下げるホルモン(インスリン)を大量に出してしまいます。
こんな例えで考えてみましょう。
人間が砂糖を食べると血糖値が上がりますよね。
そうすると体は「血糖値が高くなった!下げなくちゃ!」とインスリンを出します。
でも、犬がキシリトールを摂取した場合、
実際には血糖値は上がっていないのに、
「血糖値が上がった!」と勘違いしてインスリンを出してしまうのです。
その結果、もともと正常だった血糖値が急激に下がってしまい、
低血糖という危険な状態に陥ってしまいます。
キシリトール中毒の症状
キシリトールを誤食してから30分~6時間以内に、以下のような症状が現れる可能性があります。
・嘔吐
・元気がなくなる
・ふらつく/まっすぐ歩けない
・ぐったりする
・泡をふいてけいれんする
・意識不明
・治療が遅れると命に関わる
※肝臓障害は24-48時間後に発現する可能性があります。
(翌日や翌々日の血液検査にて、肝臓の数値が大幅に上昇しているかもしれません)
※症状には個体差があります。
キシリトールガムは何粒で危険なの?
【体重5kgの犬の場合】
| 商品名 | 1粒あたりのキシリトール量 | 危険な量 |
|---|---|---|
| 市販されているキシリトールガム | 0.25-0.31g | 1-2粒 |
| 歯科医院で処方されるキシリトールガム | 0.45-0.50g | 1粒 |
※これはあくまでも目安です。
製品によって含有量は異なり、少量でも重い症状が出ることがあります。
キシリトール中毒のリスクとなる商品
キシリトールは以下のような商品に含まれています:
- シュガーレスガム
- のど飴
- 低糖質のお菓子やパン
- 歯磨き粉
- 一部の薬
これらの商品だけを注意するのではなく、
誤食のリスクを下げる環境を整備することが、何よりも大事です!
もし食べてしまったら
チョコレートやキシリトールを誤食してしまった、
または誤食してしまったかもしれない場合は、
以下のポイントを確認してください。
慌てずに、落ち着いて状況を確認する
何を、どれだけ、何分(時間)前に食べてしまったか。
以下の情報はとても重要な項目です。
・何をどれだけ食べたか
・食べてからの経過時間
・商品のパッケージ(成分表示)
・愛犬の体重(体重あたりの摂取量が重要)
後述する催吐処置(吐かせる処置)を行う際、
どれだけ吐いてくれたら安心感が高まるのかは、
この情報の精度に基づきます。
獣医師は誤食した絶対量を把握していません。
絶対量を把握しているのは、誤食した愛犬自身だけであり、
次に把握できるのは、現場をより正確に評価した飼い主さんです。
獣医師は飼い主さん以上の情報を得ることはできないのです!
何をどれだけ誤食した?
先にお伝えしたように、
何をどれだけ誤食されたかの情報は極めて重要です。
例えばチョコレート誤食の場合では、
・チョコレートの成分は?(ミルクチョコ?ダークチョコ?)
・チョコレートの量は?(板チョコの半分?キットカット3枚?)
・包装しているビニールや紙も食べていない?
・チョコレート以外のものも誤食していない?
など、
現場で確認していただきたいポイントは、たくさんあります。
いや、むしろ、
現場でしかわからない情報を、
現場にいるうちにしっかり確認していただきたいのです。
その際、携帯で写真を撮っておくと、客観的な情報が残りますし、
動物病院受診の際は、お互いに情報共有ができて安心します。

また、袋の破片などは物的証拠として、
捨てずに病院へ持参してください!
焦っているときの人間の記憶は、時に大きく事実と乖離してしまうものです。
焦って動物病院に駆け込んでみたものの、
実はチョコレートの匂いにつられて周囲のビニールを噛んだだけ、
なんてこともしばしばあります。
[関連記事:「犬猫の救急医が伝えたい、緊急事態リスト 犬編」もご参照ください!]
病院では何をするの?
何らかの処置が必要であれば、以下を検討します。
・嘔吐処置(摂取後2時間以内で検討)
・注射や点滴治療(必要に応じて入院管理)
・活性炭投与(毒素の吸着)
催吐処置
誤食から数時間以内の場合、催吐処置と言って胃の中身を吐かせる処置を検討します。
チョコレートの誤食では、胃の中に入った時点でチョコレートはすぐに溶けてしまい、
吐かせる処置で100%全てのチョコレートを体外に排泄させることはほぼできません。
しかし、何度か吐かせることができれば、経験的にはほとんどのチョコレートは胃液とともに排泄され、
チョコレート中毒のリスクを大幅に軽減されることが可能になります。
また、キシリトールガムにおいては、
噛まれていないガムが吐き出されれば、キシリトール中毒のリスクは低くなります(ゼロではない)。
もし、キシリトールガムが噛まれていると、キシリトール中毒の懸念は残ります。
ただし、そのまま飲み込まれてしまうよりは、リスクは減っています。
※ごくまれに、チョコと共に大量の包装ビニールを誤食するケースがあり、
催吐処置で出てこない場合、麻酔をかけて内視鏡で異物を摘出することもあります。
注射や点滴
すでに何かしらの中毒症状が出ている場合は、早急に血液検査を行い状況を確認します。
低血糖が認められれば、すぐさま静脈注射にて糖の補充を行わなければなりません。
インスリンの効果が半日近く持続する場合もあり、
その場合は、継続的に糖を補給しないと、たちまち低血糖に逆戻りしてしまいます。
つまり入院管理にて静脈点滴を行う必要があります。
また、肝臓の数値が上がってしまっている場合も、
肝臓保護のために静脈点滴を何日か継続しないといけないケースがあります。
活性炭投与
幸いにも中毒症状はそれほどではないが、
チョコレートやキシリトールの成分がわずかでも吸収される懸念のある場合があります。
この場合、誤食からの時間が短ければ、活性炭の投与を検討します。
活性炭による毒素の吸着を期待します。
ただし、正直これは「お守り」に過ぎません。
活性炭がどの程度、毒素を吸着してくれるかはわからないからです。
でも、やらないよりやっておくほうが、精神衛生上は良いと思っています。
中毒予防のポイント
中毒の予防と言うよりは、
「誤食自体をさせないこと」が重要です!
- 誤食されたら困るものは、必ず犬の届かない場所に置くか確実にしまう
- 家族みんなで気をつける
それでも尚、気をつけていても起きてしまうのが誤食事故。
起きてしまったことを後悔するより、
冷静に状況を見極め、
何を優先して行うべきかを考えましょう!
この記事が、万が一の際のあなたの行動のお役に立てることをお祈りします。
まとめ
チョコレート中毒やキシリトール中毒に限らず、
誤食という事故は、適切な予防が何よりも重要です。
症状が出てからでは手遅れになることもあるため、
誤食したと気付いた時点で、すぐに獣医師に相談することをお勧めします。
誤食が確認された場合は、慌てず冷静に状況確認をしてくださいね!
次回は、家庭でよく使用される食材の中で危険なもの、
タマネギ、ニンニク、ブドウについて詳しくお話しします。
それでは、また次回の記事でお会いしましょう!良い一日を!